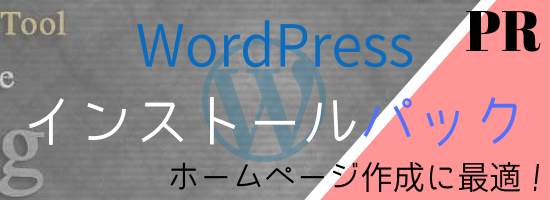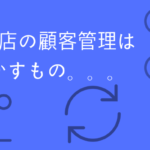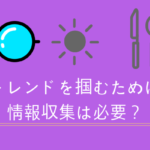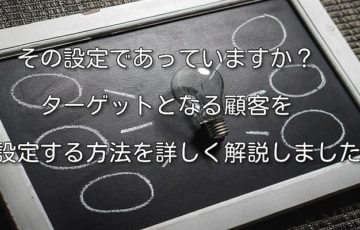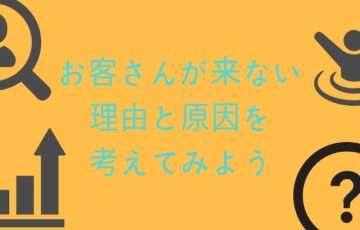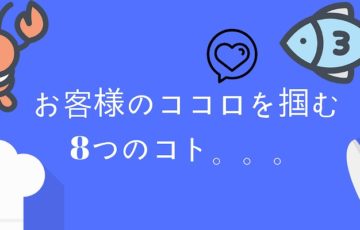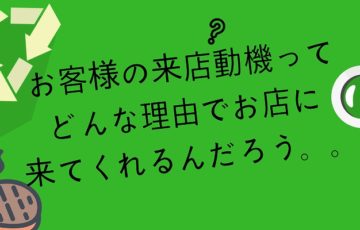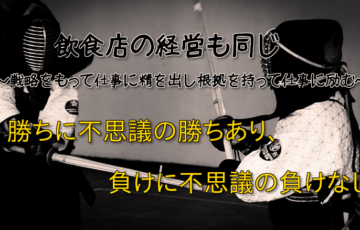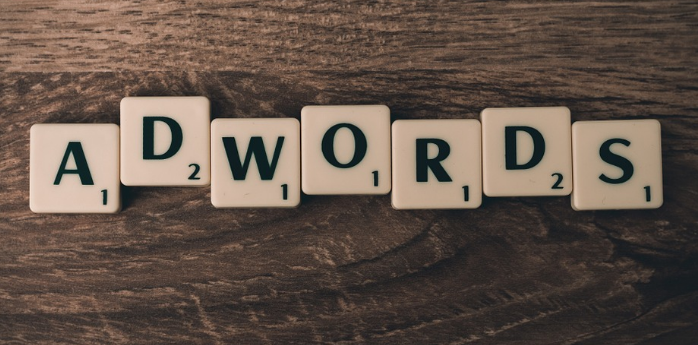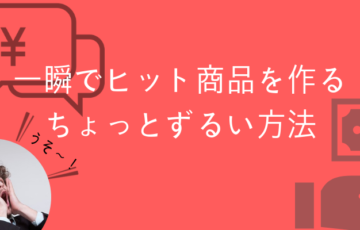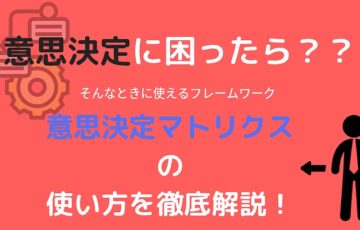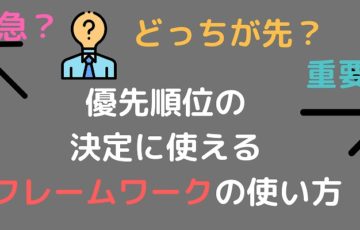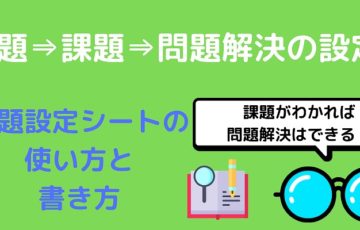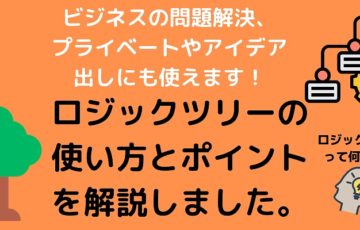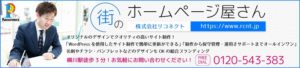どうも!
イウラ(@allezcchi)です。
飲食店で働いているとどうしてもターゲットの把握に困ることがありますよね。
そこで今回の記事ではターゲットを把握する方法について書いていこうかと思います。
お客様はどこから来ているのか?
自分の店が影響を受けている範囲のことを「商圏」といいます。
まずは、自分の店の商圏を知ることがターゲットがどこからやってきているのか知るひとつの方法です。
お客様の住所を把握するには店で発行しているサービスカード(ポイントカードやスタンプカード)、会員カードの発行、で知ることができますよね。
また最近ではLINE@などのメディアを使って顧客情報を収集していますよね。
ここであえて昔ながらのやり方でターゲットを把握していく方法も書いていこうかと思います。
店で発行しているサービスカードから商圏範囲を知る
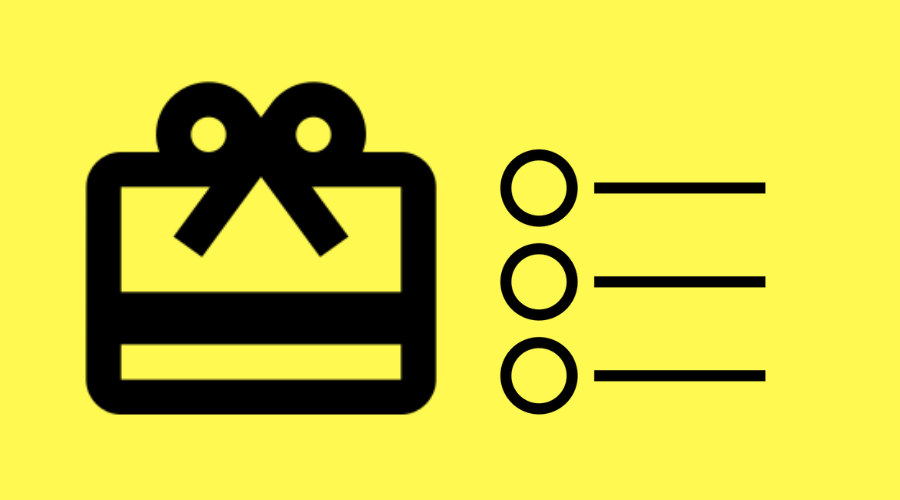
僕が料理長をしていた店ではドルチェカードというカードをお客様に渡して顧客情報を知るようにしていました。
その際、記入していただく内容は住所、年齢、家族構成、職業など細かい部分まで知ることで店のニーズを知ることができるようになります。
注意点!
この方法は顧客情報を知るにはよい方法ですが、お客様のプライバシーの管理だけは注意しましょう。
お客様の住所がわかったら地図の上に一つ一つ印をつけていきます。
一番遠いところを線で結んでみてください。
それがあなたの店の商圏範囲です。
ここで注意してほしいのは印をつけるのは常連のお客様です。
常連のお客様は情報をもらっているはずですから地図に印をつけると商圏範囲がわかりますよね。
例外として自分の店の市外に住んでいるお客様は印をつけないようにしておきましょう。
関連記事
商圏を分析する
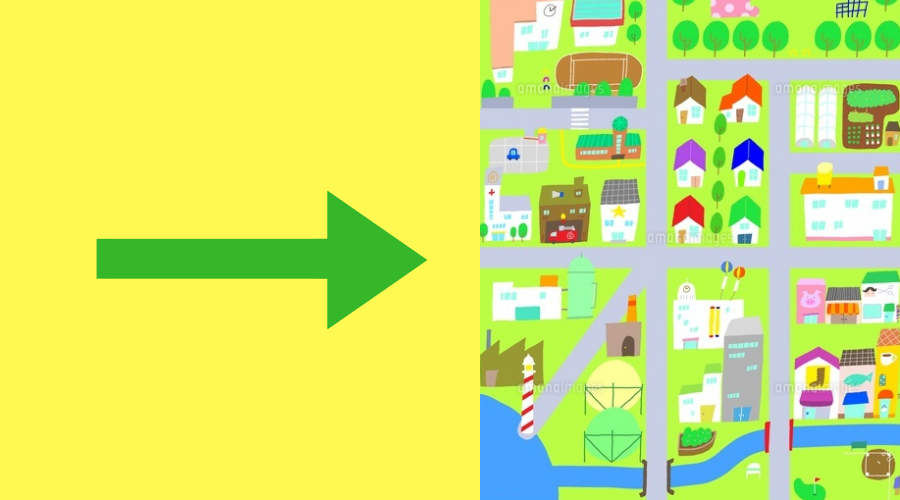
次に自分の店の商圏範囲の特徴を知りましょう。
地図を見ながら最寄の駅までの距離や通勤路にあたるかどうか、人の集まる施設(銀行や病院、会社、公共の交通機関、運動施設、大型店舗など)
が近くにあるかどうか確認します。
また店の場所にかかわる市役所や区役所などに行けばその地域の就業別人口がわかるようになります。
その中でどういった人たちが住んでいるのか知ることができるようになります。
サラリーマンが多いのか?自営業をしている人が多いのか?子供がいる家庭が多いのか?一人暮らしが多い地域なのか?
住んでいる人の層は何歳くらいの人が多いのか知ることもできます。
地域によって人の生活が変わるので自分お店の商圏範囲はどんな感じなのか分析してみましょう。
例えば長年住んでいる人なら証券範囲はある程度わかるはずです。
「この辺は昔から住んでいる人が多いので目新しい商品よりスタンダードなもののほうが受け入れられやすい」とか
「新しい住宅が多く立ち並んでいることから若い世代の夫婦が多く住んでいる。数年後はファミリー向けの業態が受け入れられやすくなるかも」
とかいろいろ考えることができます。
商圏範囲の1kmほどではどんな施設が立ち並び人々にどんな役割をもたらしているのか?
5kmではどうか?10kmではどんな店が立ち並んでいるのか調べることもできます。
その中でどれくらいの競合がいるのか調べることで競合とは違った施策を打ち出すこともできます。
自分の店の商圏範囲の中にどれくらいの競合がいるのか調べることができますよね。
まずは商圏地図を作って見ましょう。
きっとその中から施策は見つかるはずです。
商圏を活用する

さらに詳しく調査するためには店の外に出て交通量をチェックすることもあります。
本格的ではなくてもいいのです。
別に業者に頼んで交通量を調べなくてもいいと思います。
店の外から感じる風景を客観的に見ることができればマーケティングにも活用できますから
自分の目で感じるところからはじめてみましょう
交通量のチェック方法
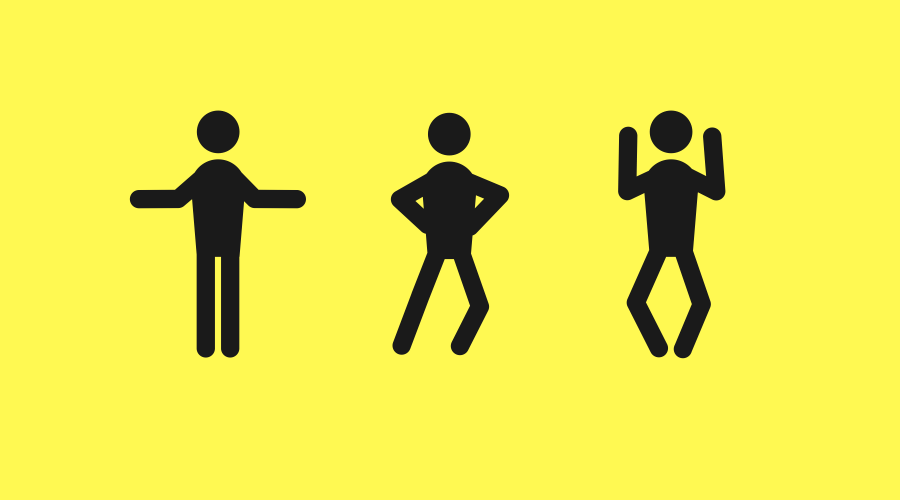
どれくらいの人がアクティブに動いているのかちょっと外に出て見てみましょう。
1分間の通行量を曜日ごとに一時間、または30分ごとチェックします。
歩いている人が多いのか、自転車を使い通っているのか、それともくるまでの通行量が多いのか見てみましょう。
また同時に通行人を観察し、年齢層や職業を推測します。
こうして商圏の特徴を掴んだら、この商圏内に住む架空の人物、、家族を創造してみてください。
年齢、職業、年収、いつもどれくらいの金額が財布に入っているか。
外食に使う金額、子供にかける金額、生活にかける金額など考えられる細かい部分まですべて紙に書いていきます。
これを考えるときは頭の中で人物や家族と相談してみてください。
また仲のよい常連のお客様に相談に乗っていただくのもいいでしょう。
とにかく架空の人物を洗い出すのです。
まるで事件を捜査する刑事みたいなことをしますが、こうやって商圏範囲にいる人を観察し分析していくんですよね。
これをペルソナの設定といいます。
推測の仕方はこちらに書いてあります
関連記事
学校ではあまり教わることはありませんが、商売をやっていく上でマーケティング能力は欠かせないのです。
他店の商圏を知る
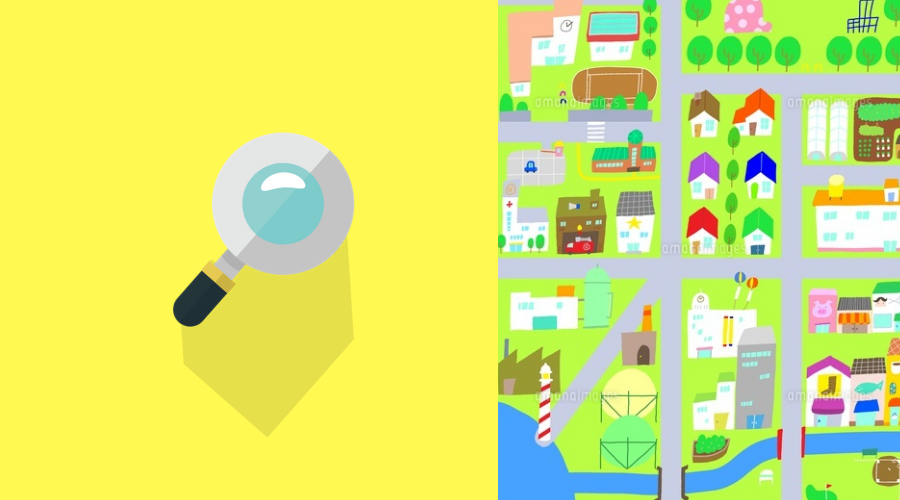
もう一度地図に戻ります。
自分の店の商圏を書き込んだ地図の上に近所にある競合店も書き入れてください。
この際は自分の店と競合の店のマーカーは違う色でチェックを入れておきましょう。
一番遠いところから来るお客様は競合店と自分の店どちらに近いですか?
競合店の近くに住むお客様が自分の店に来てくれるんだったら問題ないですが、その逆の場合だと競合店に負けているので
すぐに競合店に足を運びましょう。
実際、これをやっている飲食店の人ってなかなかいないですが、将来にことを考えると店を休んででもやっておいたほうがいいと思います。
なぜなら競合を調べないまま店を営業していると違いがわからないし、なぜお客様が競合に足を運ぶのかその理由がわからないからです。
ぜひ競合にも足を運んでみてください。
そこで自分の足りないところがきっと見つかるはずです。
求められるマーケティング能力
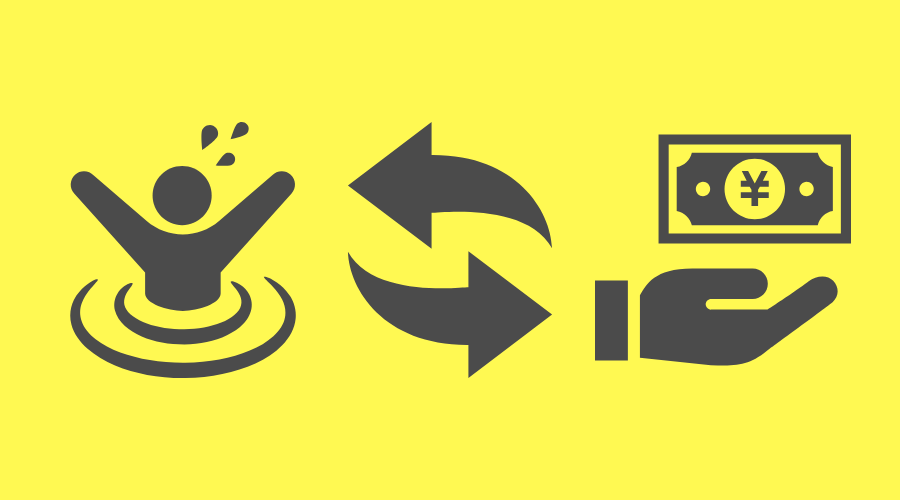
飲食業界は依然、厳しい状況にあります。
競合店の増加や人手不足など問題を挙げればきりがないですが、飲食店をやるからにはマーケティング能力は必須だといえます。
昔のようにおいしい料理を作っていたらお客さんがやってくるという時代ではないですから、自ら調査し、分析し、競合に打ち勝つことをしていかなければならないのです。
商圏範囲によっては提供する料理も価格も変わっていきます。
自分の出したい料理にこだわってばかりではいけないのです。
そのためには今一度自分のターゲットはどこからやってくるのか調べて飲食店の経営をやっていくことが大切です。
ターゲットを知れば必ず活路は見出せます。
ぜひやってみてくださいね。
まとめ
今回は昔ながらの商圏範囲についてお話をしてきました。
なぜこの記事を書いたのかというと飲食店は地域密着のビジネスだといまだに思っているからです。
インターネットの発達で今はどこにいてもたくさんの情報を知ることができます。
しかし実際に店に運ぶとしたらわざわざ遠い県外まで店を運ぶなんてことはまずありません。
よっぽどのことがない限り。
地域密着型ビジネスだからこそ、商圏範囲を知ることって大切なんです。
これは昔から言われていることですよね。
昔から店を出す前には商圏範囲を調べて出店するのが通例でした。
また国金にお金を借りるときでさえも事業計画書に商圏範囲と競合店について書かなければなりません。
改めて考えてみると飲食業界はたくさんの競合でひしめき合っています。
その中で自分の店で打ち出せる唯一の方法は何があるのかより求められていく時代です。
せめて自分の商圏範囲と競合の商圏範囲を知り、分析することで何か見えてくるのではないかと思います。
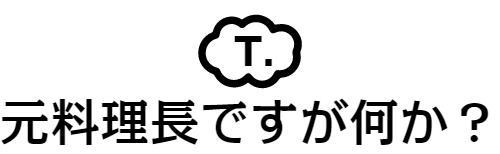
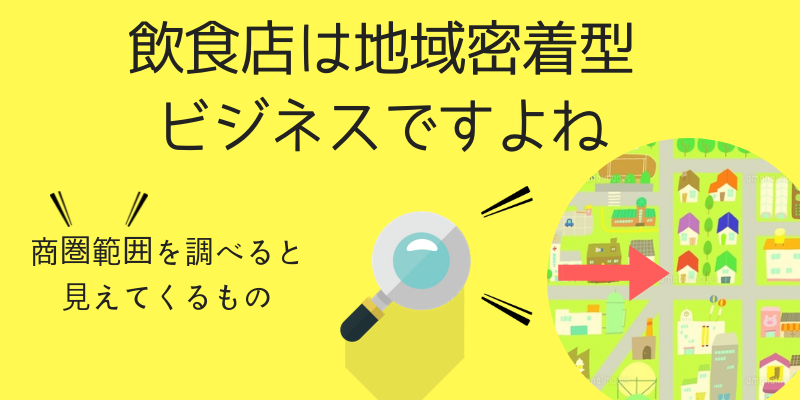


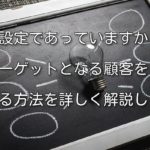
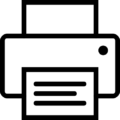 この記事はプリントできます
この記事はプリントできます